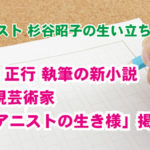ピアニストという同じ道を目指そうとする昭子にとって、一考をもたらす演奏で前半は締めくくられた。中村紘子が舞台袖に下がり、拍手の鳴り止むのを待って、昭子は自席を立ち、ロビーへと向かう。
左右、前の通路からロビーに向けて集まり出ようとする人々。「Xさん、あなたも来てたん。」「あら」っと振り返ったX。「私ちょっとお手洗い。次が始まるまで少し時間があるし、中村紘子の演奏どぉ?どこかソファーが空いていたら腰かけて待っててくれる?」暖房が効いているとはいえわずかに感じる肌寒さ、そのせいか、緊張のせいか、少しもようしぎみになった昭子。
「えぇ。私も行くの」二人は連れ立つように向かった。し終えた二人。空いているソファーに腰掛け、「昭子さん、もしまだだったら帰り一緒に食事でもして・・・?」
「えぇ、それが私もう済ませてきちゃったの」
「それでは・・・それにしても彼女、私たちよりもX歳年下で、桐朋だからなんですかね。こんなリサイタルができるなんて・・・、確かにこんなプログラムをこなせること自体すごいことね。」
昭子は話を聞き、俯きかげんに「そうね、私も弾くことだけだったらできるし、もし人前でこのプログラムをこなせたにしても、芸大の生徒としては許されないんでしょうよね。桐朋って自由のきく学校なんよね。おそらく・・・、それにしても、よく弾いているとは思うんだけど、私的にはちょっと音がガリガリしているように思えるん。プロフィールを見ると、先生は違ってても井口系なんよね。私も弾いている音、あんな音なんかね。そうだとしたら考えさせられちゃうわ。」
さだかではないにしても、昭子の胸の内には何かもっと美しくあるはずのピアノ演奏、音楽像があって、数年後、サンソンフランソアの柔らかくビロードの肌触りのようなしとやかな音楽にカルチャーショックを受けることになる。
羨望とも、同系列奏法が生み出す音色への疑問、開演のベルと共に意識はコンサートに向き行くのだった。